健康情報
「糖尿病予備群」とは?健康診断で血糖値が高めと言われた方へ分かりやすく解説

糖尿病予備群とは?血糖値が高めと指摘されたら
健康診断で「血糖値が高め」と言われて不安に感じたことはありませんか?
自覚症状がなくても、血糖値やHbA1cにわずかな異常が見られる場合、それは「糖尿病予備群」である可能性があります。
糖尿病予備群とは、正式には「境界型糖尿病」と呼ばれる状態です。糖尿病ではないものの、血糖値が正常より高く、将来的に糖尿病を発症するリスクが高い段階を指します。
放置してしまうと2型糖尿病に進行する恐れがありますが、この段階で生活習慣を見直すことで発症を防げるケースも多くあります。
健康診断で分かる「糖尿病予備群」の基準値
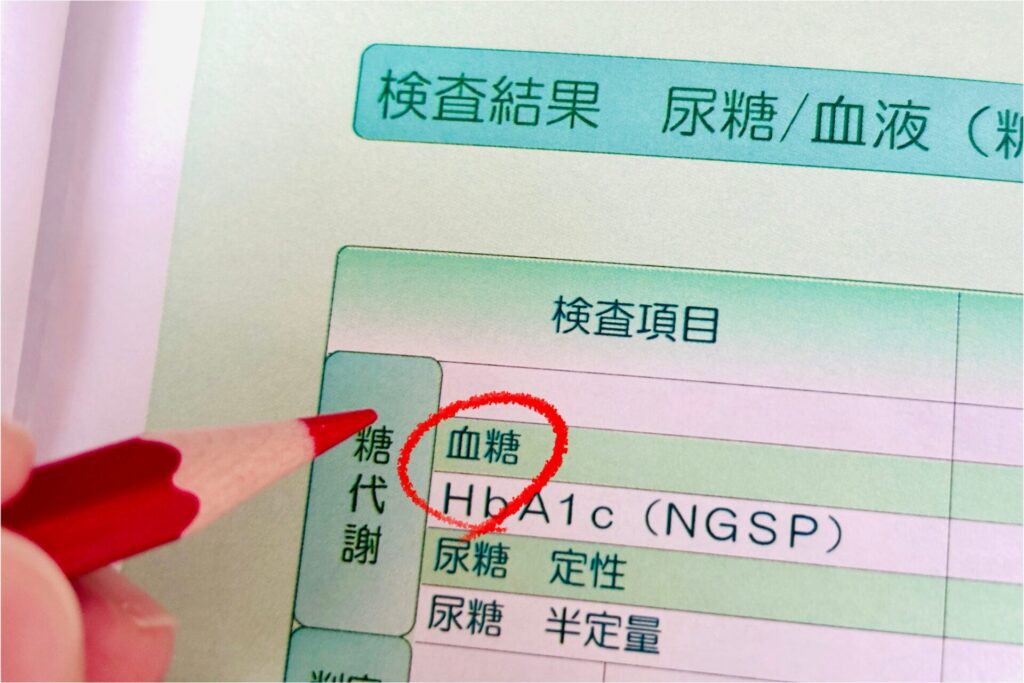
糖尿病予備群と診断される主な目安は以下の通りです。
- 空腹時血糖値:110〜125mg/dL
- 75gブドウ糖負荷試験(OGTT・2時間後血糖値):140〜199mg/dL
- HbA1c:5.6〜6.4%
いずれかに該当すると「糖尿病予備群」とされます。特にHbA1cは過去1〜2か月の血糖状態を反映するため、継続的な異常を把握する上で重要な指標です。
糖尿病予備群で起きている体の変化
糖尿病予備群の背景には「インスリンの異常」があります。
- インスリン抵抗性
インスリンが分泌されても、筋肉や肝臓でうまく作用しなくなる状態です。原因には内臓脂肪の蓄積、運動不足、過食、加齢、ストレスなどがあります。 - インスリン分泌不全
膵臓が疲弊し、インスリンを十分に分泌できなくなる状態です。特に食後の初期分泌が遅れると血糖値が急上昇しやすくなります。
この二つが進行すると、空腹時も食後も血糖値が高い「持続的高血糖」に陥り、動脈硬化や腎症、網膜症などの合併症リスクが高まります。
糖尿病予備群は自覚症状がないからこそ注意
糖尿病予備群はほとんど自覚症状がありません。
しかし、血管の内側ではじわじわとダメージが進み、将来的に心筋梗塞や脳梗塞などの大きな病気につながる恐れがあります。
「症状がないから大丈夫」と油断せず、健診で指摘された時点で生活習慣を見直すことが大切です。
糖尿病に進行しやすい要因
次のような生活習慣や体質は、糖尿病予備群から糖尿病へ進行するリスクを高めます。
- 高カロリー・高脂肪食の習慣
- 運動不足
- 内臓脂肪型肥満
- 睡眠不足や強いストレス
- 加齢(特に40歳以降)
- 家族に糖尿病がいる(遺伝的要因)
特に肥満と運動不足の組み合わせは大きなリスク要因です。
糖尿病を防ぐためにできる生活習慣改善
糖尿病予備群と診断された場合、生活習慣を改善することで糖尿病の発症を防ぐ、または遅らせることが可能です。
- 食事:主食・主菜・副菜をバランスよく。糖質・脂質のとりすぎを控える
- 食べ方:よく噛んで、野菜から食べ始める「ベジファースト」
- 運動:1日30分の有酸素運動(ウォーキングなど)を継続
- 体重管理:BMI25未満を目安に
- 睡眠:質の高い睡眠を十分にとる
- 禁煙:喫煙は血管を傷つけるため控える
「極端な食事制限」よりも、無理なく続けられる改善がポイントです。
医療機関での定期チェックも大切
糖尿病予備群と診断されたら、医師のもとで血糖値やHbA1cを定期的に測定し、変化を把握することが推奨されます。
早期に発見し、生活改善を続けることで、糖尿病の発症を防ぐことができます。
まとめ:糖尿病予備群は「改善のチャンス」
糖尿病予備群は、病気の入り口ではなく「生活習慣を見直すチャンス」です。
症状がなくても血糖値が高めと指摘されたら、それは身体からのサインです。
- 健康診断で「血糖値が高め」と言われたら放置しない
- 食事・運動・体重・睡眠を整えることで発症リスクを下げられる
- 定期的な健診と医師のサポートで「未病」対策を行える
将来の糖尿病を防ぐために、今できることを少しずつ始めていきましょう。
参考文献
- 糖尿病予備群といわれたら 糖尿病情報センター










